七五三とは本来、幼い子供の健やかな成長を祈り、祝うという日本の年中行事です。
昭和でも、1970年代頃までは幼い子供が健やかに育つ割合は今よりもかなり低いものだったので、三歳、五歳、七歳、という節目の年齢を迎えるまでに育ったということは大きな喜びだったのです。
毎年11月15日にそんなお子さんたちに晴れ着を着せて神社・寺などに「七五三詣で」を行いますが、近年ではスタジオで記念写真を残すことに熱心になる傾向があります。
三歳は主に女子(近年は男子も行うことが多くなりました)、五歳は男子、七歳は女子が行います。
- 三歳は女児が赤ちゃんの頃に髪を剃り落としていた習慣の終わり
- 五歳は男子が袴を着るようになる節目
- 七歳は女子が大人と同じ帯を結ぶようになる時期
このように、それぞれの節目にはきちんとした意味がありますので、お参りは服装を整え、節度をもって執り行うことが大切なのです。
七五三に晴れ着を着せる意味は?
七五三を迎える子供たちを連れて神社に行くのは、その神さまに対して『おかげさまでこんなに大きくなりました!』と報告するためです。
昔の、豊かでなかった時代でも、その時にできる精一杯の『晴れ着』を着せていきました。
『晴れ着』は、神さまに対する礼装なのです。
また、そんな子供たちに同行する大人たち(両親・祖父母)にも同等の格式の服装が求められます。
もし、経済的なことや、それぞれの事情で子供の着物などの用意が出来ないのであれば、親子で、その時にできるフォーマル、もしくはセミフォーマルな服装でお参りすることをお勧めします。
合わせて読みたい

また、近年はお盆などのタイミングで七五三のお参りを済ませようというやり方も、一般に認められてきています。神社でもそういったプランを提唱しているところもありますので、必ずしも11月15日前後にやらなければならない、というわけではありません。
たとえば、そんな真夏であっても、男性は襟のあるシャツにスーツのパンツ、革靴、本殿に入るときにはジャケットを着用しましょう。同様に女性もワンピースやスーツ、アンサンブルなどにフォーマルに対応できる靴を合わせることが適切です。
ただし、神社などは足元が石畳や玉砂利などを用いているところが多いので、女性の靴はヒールは低いものでも大丈夫ですが、スポーツ系のシューズは避けましょう。
子供の晴れ着と大人の服装のバランス
七五三の参拝で、お子さんだけが立派な正装で、引率している親御さんたちが普段着というのは著しくバランスを欠いています。
神さまにご挨拶するのは、お子さんだけではありません。彼らを連れて行く両親、そして祖父母がご一緒される場合であっても、全員がいずれも正装、略礼装、またはそれに準ずる服装であることが大切です。
それは“神社(神域)”という場所に対するTPOを遵守するということで、神さまに対する礼儀、そしてお参りの作法にも通じるものです。
また、写真を撮る場合、お子さんだけでなく、両親も祖父母も並んで撮影するはず。
大きくなってから、そんなスナップや記念写真を見返した時に、子供だけがオシャレをしているのも違和感がありますよね。七五三のお参りは、家族としての大切なイベントであり、子供のコスプレイベントではないのです。
ほかにもあります
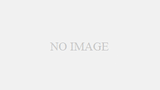
「他の人はどうしてるの?」と思ったら、体験談もありますよ♪
七五三の服装、どこまでがOKで、どこからがNG?
結婚式の招待状などで見かける「平服(へいふく)」という言葉の理解は、人それぞれに、かなり幅があります。七五三はフォーマルか、セミフォーマルな装いをするのが望ましい年中行事なので、ラフすぎるものはマナー違反です。
たとえばジーンズにTシャツ、足元がスニーカー。
ジャージなどのスポーツウェアやキャップなどの帽子。
また、ニットでもルーズな印象のあるものは、正式なお参りには適していません。
男性は、ジャケットと襟つきのシャツ、プレスしたパンツに革靴。
女性はワンピースや、きちんとした雰囲気のニットのアンサンブルなどがぎりぎり許容される範囲でしょう。
ゴージャスに着飾る必要はありませんが、清潔感のある整った印象はとても大切です。
七五三の時期の神社は、そのためにおしゃれをしてきた家族連れでにぎわいます。
そんな中で違和感を覚える格好をしていたら、その『残念』な記憶がお子さんの心にも残ってしまいます。
『みんな一緒』であることが重要視されるわけではありません。
しかし、こうした行事では、幼いなりに、その場にふさわしく『装う』ということ、またふさわしい行いを学ぶまたとない機会なのです。
まとめ
兄弟姉妹が多いと、第一子は気合を入れて準備をし、晴れ着も豪華で、スタジオで撮影した写真も沢山あるのに、末っ子は写真の枚数も少なく、適当に済ませてしまった、という方は少なくありません。
逆に、上の子の世話をしつつ下の子のそうした準備にまで手が回りかねる、という実状や、親御さんの気持ちもわかります。
しかし本来、七五三はその子供さん一人ひとりの成長をお祝いし、感謝するための機会なので、それぞれ平等に行うのが望ましい在り方です。
とんでもなく無理をする必要はありませんが。七五三のお支度と、その一日の過ごし方を、お子さんのために少し頑張ってみませんか?
親御さんやおじいちゃんおばあちゃんの気持ちは、『自分は大切に育ててもらっているのだ』という、プライスレスな心の財産になっていきますよ。



コメント